
林正盛(はやしまさもり)は、正式名を林藤左衛門正盛といい球磨川を開鑿=かいさく(山野を切りひらいて道や運河を通すこと)して、初めて海側(河口)八代から山中の人吉(相良藩の城下町)まで舟を通し、川開きをした偉人です。
林正盛の出自
林正盛は、肥後国人吉藩3代目藩主「相良 頼喬(さがら よりたか)」の母の弟にあたります。
丹波国(現・京都府)篠山に住む片岡正秀(かたおかまさひで)の三男にあたり、承応年中(1652年~1655年)には人吉・球磨(現・熊本県人吉市と球磨村)に来て商業を営んでいました。
林正盛(はやしまさもり)のデータ

出典:林正盛が川開きをした急流「球磨川」
| 氏名・職業・来歴 | |
| 姓名 | 林正盛 |
| 生存年月日 | 1621年~1697年(江戸時代) |
| 出身 | 人吉藩(現・熊本県人吉市) |
| 職業 | 商人・治水家 |
| 来歴 | 1621年(元和7年)- 片岡正秀の三男として丹波国(現・兵庫県)に生れる。 1662年(寛文2年) – 厄払いのために球磨川の開鑿をはじめる。 1665年(寛文5年) – 人吉から八代までの舟運便を開通させる。 1666年(寛文6年) – 肥後国人吉藩3代目藩主「相良頼喬(さがらよりたか)」が正盛の自宅を訪れ、その功績を賞して様々な品(袴・羽織・盃・茶道具・長刀・馬・膳椀二十人前など)を賜われた。 1697年(元禄10年)11月12日 – 没。享年76歳。 |
林正盛(はやしまさもり)の偉業
江戸時代前期に活躍した肥後人吉藩の林正盛(藤左衛門)は、どのような偉業をなし得たのでしょう?
ここでは、林正盛の成し遂げた「球磨川の舟運の川開き」について、詳しく説明します。
球磨川とは?

出典:清流球磨川・川辺川を未来に手渡す流域郡市民の会
まず、最初に「球磨川」についてです。
球磨川は、上流を熊本県球磨郡水上村の銚子傘(標高:1489m)にもち、そのまま人吉盆地を貫流し下流部である八代海=不知火海(八代市)にそそぐ一級河川で、石灰岩でできた山の谷間に、途中いくつもの支流が注ぐため激流が生まれやすく「日本三大急流」の1つとして知られています。
林正盛登場以前の球磨川の交通
林正盛が、開さくする以前の球磨川は大小さまざまな奇岩や礁=しょう(水面にあわられていない岩・隠れ岩)が点在し、川の両岸の岩壁が舟の通行を不能にしていました。
よって、当時に八代や海側から球磨郡に入るためには、険しい山越え・悪路の川沿いの道を幾度と通るしかありませんでした(主に陸路で佐敷湾へ出るルート)。
林正盛が、球磨川の舟運工事をしたきっかけ
林正盛が球磨川の川堀をはじめたきっかけは、正盛「球磨川掘記録」に書かれています。
当時の球磨川は舟で通行できないので、いろいろと工夫をこらし「お殿様の参勤交代」や「そこに住んでいるすべての民(たみ)」のことを考え「荷物をもった舟を通して、運送の便利化をはかりたい」と心から思ったといいます。
林正盛は、京都府の丹波国篠山の生まれで「球磨地方」にきて、御用商人=ごようしょうにん(封建領主の庇護のもと関連する物資を調達する特権を与えられた商人)として、一定の財を築いていたと考えられています。
「球磨川」の開さくをはじめた1662年(寛文2年)は、人吉・球磨の第2代藩主「相良 頼寛(さがら よりひろ)」が隠居し、長男の相良 頼喬(さがら よりたか)が23歳で家督を継いだタイミングです。※正式には1664年(寛文4年)
正盛は、頼喬(よりたか)からみると母の弟(叔父)にあたり、当時41歳であった彼を23歳のお殿様は「おじさん」のように気軽に接し、逆に林正盛は自分の親類である頼喬の「江戸までの参勤交代」を少しでも苦労なく楽させてあげたいと思ったのではないでしょうか?
そして、41歳の厄除けの意味もこめ林正盛は私財(自分のお金)を使って、石屋5名を連れて川筋をしらべ彼らと念入りに話し合い仕事を任せることを決め、その川舟運搬のための開さくを藩庁に願い出たようです。
球磨川の工事はうまくいったのか?
林正盛の球磨川の河床を開削する工事は、1662年(寛文2年)の春からはじまりました。
石工と人夫=じんぷ(雑用の力仕事をする労働者)を雇って、神瀬(こうのせ)多武の木から川上の石割と川堀にとりかかりました。
亀石の存在
大瀬の川下(球磨村大瀬)に亀石と呼ばれる巨大な岩がありました。
この岩があまりにも堅くて、石工でも移動や砕くことができませんでしたが、この亀石を取り除かなければ舟の通行をさまたげてしまうという大問題が生まれました。
きつねのお告げ
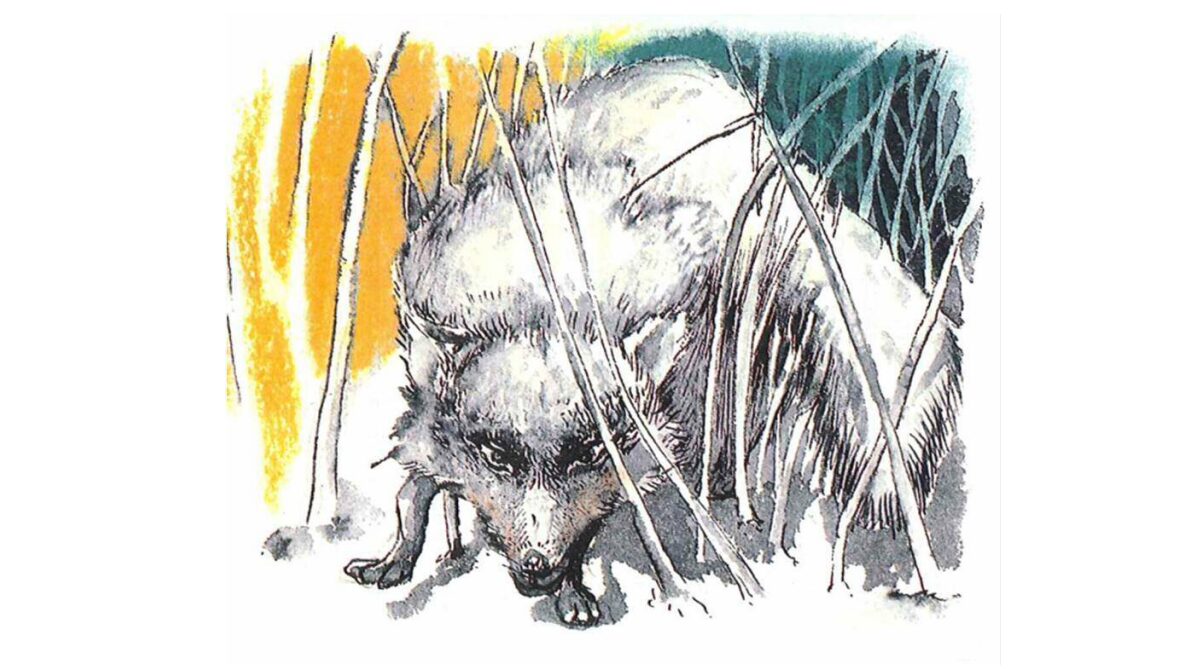
画像出典:球磨川教材化資料集(第二集)
石工(石屋)でも堅くて手におえなかった球磨川大瀬流域の巨大岩(亀石)。
林正盛は、神仏へお願いをしたところある日、一匹のキツネを見かけそのキツネに向かって「この瀬の石をけずる方法がない、教えてくれ」と言って頼んだところ
その晩の夢にキツネがあらわれ「石の上に大火を焼き、そのときに良く割る。その割れた石を捨てて、また火を焼きをくりかえすと7日以内に残らず片付く」というお告げがあったのです。
それより、人夫に薪=まき(火をつける木)数百をまとめて燃やさせ焼き通ったところまで割るという作業に徹して、3日以内に残らず、亀石は除去できたのです。この工法は火力で岩を熱し水で冷却=石の膨張・収縮を応用した技法として有名です。
これがきっかけで、この場所を亀割(かめわり)と呼ぶようになり、正盛宅に稲荷社を勧請=かんじょう(離れた土地の神社から分霊を迎え、新しい神社に祀ること)し末永く信仰したようです。
※この話は、むかしばなしとして球磨川教材化資料集(第二集)ふるさと八代球磨川に収録されています。
亀の字の焼き印

出典:岩の山に囲まれ流れに勢いがある球磨川
亀石が割れて巨大石が除去できたことを受け、正盛は「神の御力ゆえに、今後も川船通行で万民の難儀をお助け下さい」という意味をもって、船を通行させるときの鑑札(舟の行き来に許可を与えたことを証明する証書)に亀という焼き印を押し、水主=かこ(舟のかじ取り以外の水夫、または船乗り)に渡しました。
球磨川はいつ開通したの?
球磨川の開削が終了したのが林正盛44歳のとき1664年(寛文4年)で、翌1665年(寛文5年)から川船が通うようになりました。
まず、八代御假屋(球磨川河口に設けられていた湾岸施設)の舟大工「山城氏」に川舟を作らせ、球磨川に初めて舟を浮かべ、その後神瀬多武の木から一勝地・大坂間まで試験的に川をのぼって成功し、着舟しました。
その後も、林正盛は一勝地内の石割りをし、渡(わたり)と三ヶ浦(さんがうら)の石を取り除いて、八代から神瀬、そして人吉までの難工事をのりこえ、水路の開さくに成功しました。
球磨川の舟運が開けたことで変わったこと
球磨川の舟運が通っていないときは、人吉から神瀬多武の木まで人夫にて陸路で運んでいたため、お米などの物資の輸送もここで「多武の木米おとし賃」という別料金が発生していたようです。
これが無くなり、人吉から八代までお米・いもその他の品物を自由に舟運で積み下ろしできるようになって、人々はたいへん喜んだといいます。
1668年(寛文8年)には、人吉のお殿様である相良 頼喬(さがら よりたか)が28歳にしてはじめて、青井阿蘇神社前の祓川から船で八代まで出ました(それまでは陸路で佐敷湾へと向かうルートでした)。
林正盛の功績を称える
林正盛が球磨川を開削してくれたおかげで、人吉から八代までの舟運が開通し、その労と栄誉をたたえ毎年3月1日の「球磨川下りの川開き」の日には、人吉城内にある頒徳碑の前で「碑前祭」が開かれ、一年間の川下りの安全祈願がなされます(1924年=大正13年2月11日に林正盛に従五位下の贈位があり、人吉城内に林正盛翁頒徳碑が建立されています)。
また、林正盛の墓所(人吉市南願成寺町岩清水の高台にある)では、命日11月12日に子孫が集まり、しめやかに墓前祭がとりおこなわれています。
林正盛の偉業は、鉄道や車などの新時代の輸送が普及するまで、宮崎・鹿児島から熊本へ往来する旅人や、地元(芦北・八代・人吉球磨)のさまざまな物流・人流に多大なる影響を与えました。※①
※①1908年(明治41年)6月1日に八代と人吉を結ぶ汽車が開通するまで、260年の間

